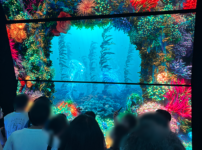『漫画 会計の世界史』を読んで興味を持ったルネサンス時代。芸術家がとても活発だった印象が強い。
実は、ルネサンス時代に芸術家が活躍した背景には、「会計」の発展が大きく関わっています。
💡会計と芸術家の関係
- パトロン制度の確立
- 当時、芸術家は貴族や富裕な商人、教会からのパトロン(スポンサー)の支援を受けて作品を制作。
- パトロンたちは、芸術作品に投資することで、自らの権威や富の象徴としたり、宗教的な功徳を示す。
- そのため、芸術家は安定した収入を得られ、作品制作に専念できる環境が整う。
- 複式簿記の発明
- ルカ・パチョーリが1494年に発表した『算術、幾何、比および比例のすべて(Summa de Arithmetica)』で、複式簿記(ダブルエントリーシステム)が紹介されました。
- これにより、パトロンたちは資産管理や支出の記録を正確に行えるようになり、芸術家への支援を計画的かつ持続的に行うことが可能になりました。
- 金融の発展が芸術を支えた
- ルネサンス期には、銀行業や信用取引が発展しました。
- 特に、メディチ家のような金融業者は、芸術家への支援に積極的で、銀行業の利益を芸術文化に再投資しました。
- その結果、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなど、多くの芸術家が生まれたのです。
この時代から、神や神話だけでなく、庶民の生活や日常風景が描かれるようになったのも見所です。
それまでは、宗教画や権力者の肖像画が主流だった絵画の世界に、普通の人々の生活や自然の風景が登場したことで、アートが一気に身近な存在になったらしいです。
レオナルド・ダ・ヴィンチ
《モナ・リザ》

圧倒的な存在感。時代を追って名画を見てきた中で、特にこの《モナ・リザ》を見たとき、思わずハッとしました。
よく知っているはずなのに、まるで初めて出会ったような感覚。まさに「見えない何かに引き寄せられる、魅了される」とはこのことか!と改めてこの絵の凄さを感じた。
・スフマート技法:境界線が見えないため、「モナリザ・スマイル」と呼ばれる神秘的な微笑みが生まれました。見る角度や光の加減で、表情が変わるように見えるのもこの技法の特徴です。
・モナリザのモデルは特定されていないけれど、実は目元にあざがあり、病気を患っていた可能性があるとか。
レオナルド・ダ・ヴィンチの作品は、医学や解剖学の知識も反映されていて、単なる「美しい女性像」にとどまらない、人間の内面や真実を描き出す力があると感じました!
《最後の晩餐》
修復前と修復後の2種類が並べて展示されているのも、興味深いポイントです。
学生時代に「裏切り者は誰でしょー?」ってお題が出たことを思い出しました。
人が多すぎて全体の写真が撮れなかったので、以前行った時の写真を載せます。

『レオナルド・ダ・ビンチ (世界の伝記 コミック版 47)』を読みましたが、彼は、絵画だけでなく、解剖学や建築、発明、哲学など、あらゆる分野に興味を持ち、常に学び続けた人。まさに「万能の天才」です。
私も、レオナルド・ダ・ヴィンチのように、日々の小さな疑問を大切にし、学び続ける姿勢を持ちたいと思います。そして、デザインやクリエイティブな仕事に、ダ・ヴィンチのような探究心と好奇心を活かしていきたいです!
ミケランジェロ
システィーナ・ホール
美術館入ってすぐに目に飛び込んでくるのは、ミケランジェロの作品が描かれたシスティーナ礼拝堂。
この礼拝堂には、『天井画』と、『最後の審判』が描かれています。
どちらも同じ場所にありますが、テーマが異なります。
《システィーナ礼拝堂天井画》 (1508年〜1512年)
システィーナ礼拝堂の「天井」に描かれており、旧約聖書の『創世記』から、天地創造、アダムとイブ、ノアの物語などが描かれています。

・ミケランジェロは本来彫刻家だったのに、教皇から「絵を描け」と命じられて『システィーナ礼拝堂天井画』を制作することに。
・「アダムの創造」のポーズ(神とアダムが指先を伸ばしているシーン)は、映画『ET』(ETと少年の指先が触れる場面)のインスピレーションになったとか!
🌟デザインの気づきと学び🌟
・名画から「構図」や「ポーズ」のヒントが得られる。
・視点や距離を計算し、見る角度に合わせて描く工夫。
・専門外の仕事でも、頼まれたら挑戦してみる。新しい分野での経験が、意外な成果を生むこともある!
《最後の審判》 (1536年〜1541年)
同じシスティーナ礼拝堂の「祭壇壁」に描かれた壮大なフレスコ画で、キリスト教における「終末の日の魂の裁き」がテーマ。
特徴: 天国に昇る者と地獄に落ちる者がダイナミックに描かれています。

・全ての人が筋肉質に描かれているのもミケランジェロの個性なのかな。
・この絵の批判者を地獄の王ミノスとして皮肉った描写も!(右下写真)ロバの耳(愚か者の象徴)をつけ、さらにヘビに股間を噛まれているという、かなりえげつない表現になっています。笑
批判者は怒って教皇に「消してください!」と頼んだけど、教皇は「天国でも地獄でも私は何もできない」と一蹴してミケランジェロの勝利!
ルネサンス期は芸術家が地位を確立しつつあった時代で、アートは単なる注文品ではなく、アーティストの個性や意思を示す「反撃の舞台」にもなり得たのだろう。
・フレスコ画は、湿った漆喰(しっくい)の上に水性絵具で描く技法。乾く前に描き切らないと修正ができないのが特徴です。
そんな難易度MAXな技法で、ミケランジェロはほぼ1人で『システィーナ礼拝堂天井画』を完成させた。絵具が目に落ちてきて視力を落とすほどの過酷な作業だったとか…まさに大大大偉業すぎる!この作品で自身を抜け殻のように描いているのを見ると、「この仕事で精魂尽き果てたのを表現してるのかな?」なんて思ったり。
ケランジェロ自身の信仰や人間観、そして反骨精神がぎっしり詰まった本物の作品をいつか見てみたいです!
サンドロ・ボッティチェッリ
レオナルド・ダ・ヴィンチと同じフィレンツェの芸術家であり、メディチ家のパトロンを持つなど、同じ時代・環境で活動していました。
代表作《ヴィーナスの誕生》 (The Birth of Venus, 1485年頃)
前にAdobe Illustrator のソフトウェアのパッケージに使われていたので、30〜40代以上のデザインやアートに興味がある人には馴染み深い作品だと思います。実物サイズは約 172.5 cm × 278.5 cm で、思った以上に大きい!


《春》 (プリマヴェーラ, Primavera, 1478~1482年頃)
神話の登場人物たちが、豊穣や愛、春の訪れを象徴するシンボルとともに描かれています。
特に、中央に立つヴィーナスや、花をまき散らすフローラの描写が印象的です。
植物や花の細部まで丁寧に描かれていて、植物学的にも貴重な資料とされています。
右側の人の対比の色合いを見て、「この配色、今後のデザインに活かせそう!」と感じました。
まとめ
ルネッサンス時代の繁栄は、芸術家たちがパトロンの支援を受けて、存分に創作に打ち込めたからこそ実現しました。制作や創作活動は、十分な時間と資金があってこそ、より良い作品が生まれるものだと改めて感じました。